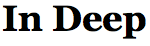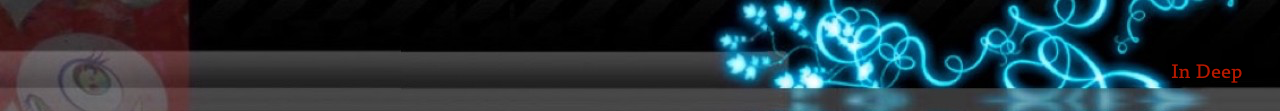2016年7月1日のロシア・トゥディ記事より
 ・RT
・RT
今回は、この冒頭の記事をご紹介しようと思います。
この記事の内容に現れていることは、今の社会の中では、何かの事象に対して、「まず憎悪が表面にあらわれやすい」ということを意味している気がしまして、やっぱりそれはどこかで軌道を直していかないと、とは思います。憎悪と憎悪が対立しても、その先には、さらに大きな憎悪が誕生するだけだからです。
上のイギリスのヘイトクライム(憎悪の犯罪)は、主に移民などに向かってのものですが、現状、世界の難民の数は「過去で最も多い」ということになっています。
世界の難民や避難民、第2次大戦後最多に 6530万人
CNN 2016/06/21
国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が「世界難民の日」に当たる20日に発表した報告書によると、世界の難民や避難民の数は第2次世界大戦後を上回り、過去最多になった。
難民認定申請者や国内避難民、難民の総数は2015年末の時点で6530万人に達し、世界で113人中1人に相当する。前年に比べると580万人増えた。
難民の出身国はシリアが最も多く490万人、次いでアフガニスタンの270万人、ソマリア110万人。この3カ国でUNHCRが対応する難民1610万人の54%を占めた。
今は世界大戦がまだ起きていない時だというのにこれでは、本格的な大きな大戦などが起きた場合は、世界がムチャクチャな混乱に陥るのは明白な感じですが、現時点でも、こういう状況で、本格的な「憎悪と憎悪の対立」が起き始めると、収集がつかなくなることもないではないような気がします。
あまり関係ない話となりそうですが、冒頭の本記事の前に、どうしてこういう憎悪が拡大しているのだろうという、まあ、余談を書かせていただきました。
Sponsored Link
親が子どもに教えるべきこと
私の父親は定年まで小学校の教師をつとめた真面目な人でしたが、タワシは、じゃない、私は、小学校時代を含めて学生時代に、父から「勉強しなさい」と言われたことは一度もありませんでした。
ただし、父親は、「女の子や弱い人をいじめたり、差別するようなことだけは絶対にやってはいけない」と、よく私に言っていました。
というか、それ以外のことで、父親から「○○をしなさい」と言われたことはないです。基本的に、ほとんど自由にさせてくれた父親でした。
そういう父の言いつけは、ある程度守って生きてきたと思います。
まず、「勉強をしない」ということは徹底していて、私は家で勉強した記憶がほとんどありません。受験の時も勉強したという記憶がほとんどないですので、「家で勉強をしない」ということだけは守り通した学生時代でした。
教科書のたぐいは、中学高校では、確か学校の机の中に入れっぱなしでしたので、手ぶらで登校できていたように記憶しています。
そのようなこともあり、私は自分の子どもにも、家ではなるべく勉強をしないように勧めています。
学校ではともかく、子どもは家で勉強するよりも、それがどんな下らないことであっても、自分の興味のあることに熱心であるほうがいいと思っています。
それと共に「小さなときは勉強しないほうが成績が上がる」ということを、私自身は経験則として真理だと思っています。しかし、それに対しての理由付けはできないだろうなあと思っていたのですが、過去記事の
・シュタイナーが「子どもへの詰め込み教育は絶望的な社会を作る」といった100年後に、完全なるその社会ができあがった日本…
2015/04/16
という記事で書きましたが、ルドルフ・シュタイナーが「詰め込み教育は、子どもの能力の成長を阻害する」ということを 1912年の講演で述べていたことを知り、「ちゃんとした理由もあったんだなあ」と納得した次第でした。
シュタイナーは、小学校に詰め込み教育が導入されたら、もうお終いだというようなことを述べていましたが、それは今、日本では特に現実となっています。
実際、日本が本格的に「詰め込み教育 + 塾」という狂気の世界に突入して以来、日本の学力は落ちる一方です。
東京大学の世界ランキング
2005年 16位
2006年 19位
2007年 17位
2008年 19位
2009年 22位
2010年 26位
2011年 30位
2012年 27位
2013年 23位
2014年 23位
2015年 43位
ついには、最近は、東京大学がアジア大学ランキングで7位に転落という報道もあり、日本の学力低下はかなりのものですが、詰め込み教育が続く限り、この傾向は止まらないと思われます。
明治や昭和の頃、日本が数々の優秀な経営者や科学者を輩出していた時、その彼ら彼女たちの子ども時代は、ガリガリと暗記につぐ暗記の詰め込み学習をさせられていたでしょうか。
また、世界の大学ランキングで上位にある欧米の国や地域の教育で、詰め込みという概念を教育に持ち込んでいるところはないはずで、子どもが自主的に考えることがどれだけ大事かということを、もはや日本の教育は忘れています。
とはいえ、子どもに対してどのように対応するかは、それぞれのご家庭や親御さんなどの問題ですので、これは単なる個人的な感想です。
そんなわけで、「なるべく勉強をしない」という家訓のほうはいいとして、父親がよく言っていた、
「絶対に弱い者をいじめたり、差別してはいけない」
という概念は、それぞれのご家庭の教育方針とは関係なく、子どもたちが体得していかなければならないことだと思いますので、どこのどんな親でも、子どもにそのことを言い聞かせなければならないことのように思うのですが、実際にはどうなのかなと。
私にしても、どうなのかなと。
「弱いものを攻撃しない」という考え方の基盤にある概念は「慈悲」ですが、今の世界は、日本も含めて、この「慈悲」という概念が基本にないのが現実のような気がします。それは、メディアの報道などを見ても感じます。現在の報道には、「弱い者をとことん叩く」という側面を感じることがあり、私は子どもには、なるべくニュースを見てもらいたくないと思っています。
あと、政治にもなるべく関心を持ってほしくないと思っています。民主主義の政治というのは、日本も米国もそうですが、「相手の弱点を見つけて、とことん叩く」、あるいは「相手に攻撃だけをし慈悲はかけない」というのが基本となっていて、それは、私が自分の子どもに最もなってほしくない人格だからです(これは政治家の方を非難しているのではなく、民主主義全体を非難しているだけのことですので、政治を志す方は気になさらないで下さい)。
「慈悲」がある感情のもとに「憎悪」は産まれないのだとすれば、冒頭のイギリスの「ヘイトクライム(憎悪犯罪)が 500%上昇した」というのも、このことに、イギリスという国の(一部の)人たちの根底にあるのが「慈悲ではなく、憎悪」であるということが示されていると思われます。
現代社会において、この「憎悪」を作り出している根本的な原因が何かというものは、あくまで個人的な観念ですが、薄々ながらわかってきています。
しかし、それはあまりにも根本的な問題で、加えて「逃げようがない問題」としか言いようがないことですので、それを書いてしまうと、気づいてしまった人たちが異様な脱力感に襲われてしまう気もしないでもないですので、今はふれないです。
話を戻しますと、子どもの頃、父親から「弱い者をいじめたり差別したりしてはいけない」と言われて、比較的それを念頭に置いて生きていましたので、大人になってからも、基本的に差別やいじめることなどを考えることなく生活できているということには感謝したいです。
そしてですね。差別というような概念を持たずに長く生きていると、「差」というものについての感情が弱くなるのです。
たとえば、最近、「格差社会」という言葉を聞きます。それで怒ったりしている人の姿を見たりすることがあります。こういうのが私にはわからないのです。
まあしかし、人の意見はいろいろですので、それはいいとしても、たとえば誰かに対して羨むとか妬むとか、そういうのも「差に対して感情を抱く」ということのひとつだと思うのですが、「差は差として存在している」という事実があっても、そこに感情を付随させなければ、嫉妬だとか憎悪などは本来は起きないはずです。
人間は、たとえば小さな子どもの時は、自分と他人に物質的な差があっても気にしないものです。ということは、「成長の中の段階で、差に対しての嫉妬や憎悪を何らかの手段で学習させられてしまっている」ということになると思うのです。
この本質は陰謀論の世界にも似たもので、日本には、少なくとも江戸時代くらいまでは、庶民には「物質の差を、人間の差」としてとらえる考え方はなかったですので、どこから持ち込まれた概念なのかはとてもわかりやすいです。
慈悲を意識することの重要性
話が逸れましたが、とにかく、できるだけ私たちは若い世代に、「最も大事なことは慈悲である」ことを伝えていかなければならないのですけれど、私にしても、どうもうまくできないというのか。
あと、「感謝」もですね。
「慈悲」と「感謝」が社会に広まれば、劇的に社会は変わるはずで、それによって病気も減っていくであろうことは、昨年の記事、
・オカ氏の異常な愛情 または私は如何にして心配するのをやめて恐怖を愛するようになったか
2015/08/08
などに書いたことがあります。
あるいは、
・世界を変えるかもしれない「瞑想という革命的存在」 : 英国の大学が「たった7分間の慈悲の瞑想が人種的偏見を人々から著しく減少させる」ことを発見
2015/11/20
という記事では、お釈迦様の「慈悲の瞑想」が、いかに「差別的意識を減少させるか」ということを記しました。
白人の成人 71人を対象にして、
・慈悲の瞑想を「7分間」おこなったグループ
・慈悲の瞑想をおこなわずに他の方法をおこなったグループ
とわけておこなった後に、無意識の態度を測定するプログラムで感情の変化を計ったところ、「慈悲の瞑想」をおこなったグループは、差別的な感情が減少し、「他人の利と幸福を考えるという感情」が増加したという明らかな結果が出たのです。
その「慈悲の瞑想」は、上の記事の後半にありますが、特徴は、
「私は幸せでありますように」
から始まり、
「私の嫌いな人々も幸せでありますように」
を経て、
「生きとし生けるものが幸せでありますように」
という流れとなっていて、自分を慈しむことから始まり、嫌いな人をも慈しみ、そして、すべての生命を慈しむ。
本当は今のような時は、世界中の人たちがこの慈悲の瞑想をおこなったほうがいいような局面のような気はしますが、そういう方向には行かないですね。
長くなってしまいました。
ここから、ロシア・トゥディの記事です。
この記事を読みますと、イギリスの EU 離脱の国民投票そのものが、「ちょっとしたパンドラの箱」だった可能性があることがわかります。
‘Shocked and disgusted’: Hate crime reports jump 500% since Brexit vote – UK police chief
RT 2016/07/01
衝撃と嫌悪 : EU離脱投票後にヘイトクライムが500%増加したとイギリスの警察署長は述べる
ブレグジット(イギリスの EU 離脱)を決める国民投票の後、ヘイトクライムが5倍に増加したことを、英国警察はオンラインサイトで公表した。
地元当局者はまた、移民たちに対しての言葉の暴力と物理的な直接暴力の両方が増加していることを指摘した。
国民投票がおこなわれた 6月23日以降の 1週間で 331件のヘイトクライムが報告されたが、平均の 1週間で起きるヘイトクライムの件数は 63件なので、5倍ほども増加したことになる。
サラ・ソーントン英国家警察署長
 ・BBC
・BBC
国家警察署長協議会(NPCC)のサラ・ソーントン(Sara Thornton)署長は、「以前より多くのヘイトクライムが多数の人々から報告されていますが、まだ報告されていない多くのケースがあると思われます」と語る。
また、イギリス全土のコミュニティで、「アンチ移民」の動きが広がっていることを指摘しながらも、ソーントン署長は、それらの憎悪犯罪が国民投票の結果と直接関係しているのかどうかを言うことは難しいと述べる。
この1週間、移民たちが暴言を浴びせられたり、あるいは少ないケースながらも、直接暴力を受けるケースが報じられている。
ソーントン署長は、イギリスでのヘイトクライムの急増に対して、「ショックを受けているし、うんざりもしています」と苛立った思いを述べる。
彼女は、憎悪の行為を受けている人たちに対して「苦しみに対して沈黙しないでください」と訴え、また、虐待を与えることで恐怖を作り出すような雰囲気を犯罪者たちに与えないでほしいと述べる。
警察の報告書は、ソーシャルメディア上に発表された。ヘイトクライムの対象となった人々は、東ヨーロッパ、特にポーランドとルーマニア、およびイスラム世界からの移民たちだった。
つい最近、ヨルダン生まれのイギリス人アーティストのヤスミーン・サブリ(Yasmeen Sabri)さんは、彼女が暴言で攻撃された話をソーシャルネット上で共有した。
それは、ロンドンでおこなわれた彼女のブルカ(イスラム世界で用いられる女性のヴェール)の展示会への訪問者によってなされた。その展示会は、訪問者たちは、見るだけではなく、ブルカの試着もできる。
その展覧会会場に、明らかに不機嫌な表情の女性が訪れ、サブリさんに近づき、暴言を浴びせた後に、展示されているブルカを引き裂こうとしたのだ。
アーティストのヤシミーン・サブリさん
 ・Evening Standard
・Evening Standard
「私がヨルダン出身にも関わらず、彼女は私に『サウジアラビアへ帰れ!』と叫びました」とサブリさんは記している。
周囲の人々が彼女をなだめようとしたが、その女性は、「アラブ人たちはイギリスの街から出て行く必要があるのよ! 彼らはここの人間じゃない!」と叫び始めたという。
サブリさんは、ロンドンに移住して6年になるが、その間に、このような人種的な暴言に接したのは、これが初めてのことだという。
今のイギリスでは、民族的な動機の、前例のない出来事が起きている。
そこには、同級生から攻撃を受けた上に「これ以上のポーランド害虫はいらない」と書かれた紙をポストボックスに投げ込まれたポーランドからの8歳の移民の女の子の例も含まれる。
この事件の発生を受け、キャメロン首相は、移民たちに十分な安全が提供されるように警察への資金を増強することと、ヘイトクライムに関連した検察官に新たな指針を与えることを誓約した。
キャメロン首相は、「これらの攻撃は悲惨な出来事であり、そのようなことはすぐにやめなければならない。そのような犯罪は非難されるべきものだ」と述べ、ヘイトクライムに対して、政府は最大の努力をするとした。
アンチ移民感情は、投票前にすでに英国で高まっていた。アンチ移民およびアンチ難民などの文言は、多くの場合、イギリス独立党(UKIP)などの右翼勢力によって採用されていた。
イギリスでは、イスラム移民に対して断固たる擁護の立場を取っていた労働党所属の女性下院議員ジョー・コックス氏が、国民投票の前、極右政党支持者と見られる男に刺殺されるという陰惨な事件も起きている。