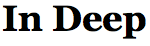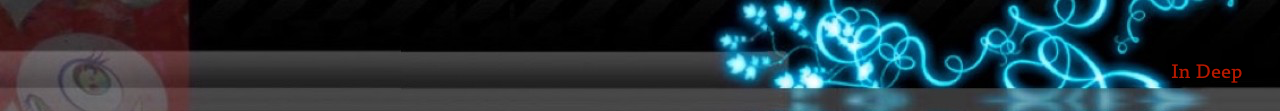気を抜くと、すぐに暴飲に走ってしまいます。そして、この2日ほどいろいろその系がありまして、今日はすっかり体調を崩してしまいました。
ちなみに、上の写真は本文と何の関係もないですが、写真がないのもさびしいですので、2013年3月19日にフロリダで撮影された雲を。
それにしても、先日は、
・最大M6.2を筆頭に、M4.5以上の地震が「1日で13回連続して発生」した9月23日の関東沖…
2016/09/24
という最近の地震のことを少し書いたのですけれど、相変わらず国内の地震が多いですね。
今日も少し前に、「鹿児島・奄美で震度5弱 (産経ニュース 2016/09/26)」と、マグニチュード5.7の地震が起きていたようですし、その少し前には北海道でマグニチュード 5.5の地震が起きていたり、昨日と今日を見ますと、佐渡で連続して地震が発生したりと、ちょっとふだんと様相が違うような感じもあります。
2016年9月25日と26日の日本で震度を記録した地震
・気象庁
しかしまあ、地震はともかく、何より体調管理をしていないと、災害に備えるも何もあったものではないです。
江戸時代の貝原益軒さんによる『養生訓』には、下のようにあります。
貝原益軒『養生訓』第三巻の一
人とは、天と地から生まれてきた。しかし、人が元気に生きていくには飲食により養分を毎日とらなければいけない。たとえ、半日でも飲食をぬかすことはよくない。
でも、飲食とは欲望の一つである。欲望のおもむくままに飲食を続けることは、胃腸によくない。度を過ぎれば、生命にもかかわることである。
胃腸から取り込まれた養分が、身体を養っている。草木が土のなかの栄養を取り込み生きているのと同じ事である。
養生訓 (抄訳)より
とあり、
> 欲望のおもむくままに飲食を続けることは、胃腸によくない。
というようにしたあげく、今そのままの報いを受けております。飲食というか、お酒だけの問題ですが。
ところで、体調維持ということで思い出したのですが、以前、
・「私は素晴らしい世界に生まれて、その世界に生きている」
2016/04/25
という記事で、山本浩一さんという方が書かれた『腰痛は心の叫びである』という本のことにふれました。
思えば、この記事から、もう5か月も経っていることに驚きますが、私はこの本を読んで以来、ここに書かれてある「腰痛にならない生き方」という章にある、いくつかのことを今も行い続けています。
腰痛はもともとないですので、腰痛云々というより、これは「病気や苦痛を生まないような生き方」というような意味でもいいのかと思いますが、いろいろなことが書かれてありますが、その中で、「これはやって良かった」と最も思っていることがひとつあります。
それは、
「日常生活の中で《すみません》と言わない」
ということです。
これは、「言葉使いを変えるだけでストレスは軽減できる」というセクションに出てくるものですが、そのセクションの冒頭は、
言葉の使い方に注意を払うだけで、ストレスホルモン(アドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾール)が減少して、いわゆる脳内麻薬(エンドルフィン)やハッピーホルモン(ドーパミン)が増加することを脳科学が突き止めています。
というようなことから始まりますが、それはともかくとして、その中に以下のようなフレーズがあるのです。
『腰痛は心の叫びである』より
とりわけ避けたいのは、「すみません」です。私の経験上、慢性的に体を痛めている多くの人は、「すみません」が口癖になっています。
何かしてもらったら「ありがとう」。悪いことをしたなら「ごめんなさい」。
場面に応じた言葉がちゃんとあるのにもかかわらず、どんなことにでも「すみません」を連発してしまうのです。
「すみません」という言葉には自己否定の意味合いがあり、ありがたさよりも「こんな自分にこんなことをしてもらって申し訳ない」という気持ちを前面に出している印象を受けます。これでは、かえって失礼です。
また、自分が存在していること自体に謝罪している印象があります。
ここに、
> 慢性的に体を痛めている多くの人は、「すみません」が口癖になっています。
とありますが、まさに私が「すみませんが口癖になっている」人なのでした。
たとえば、居酒屋でもレストランでも何でもいいですが、店員さんを呼ぶ時に「すみません」と呼ぶのは、まあ、他の方でもあることでしょうけれど、その後も、私は、料理や飲み物を持ってきてくれた店員さんに無反応で接するということができなく、注文したものひとつ持ってきてくれるたびに、
「どうも、すみません」
と、いちいちすべてに反応するタイプの人でした。
あるいは、今はそういうお店には行っていないですが、かつて、女の子が飲み物を作ってくれるようなお店に行っていた時も、飲み物をつくってくれるたびに、「ああ、どうもすみません」みたいなことを言う人だったんですね。
私自身としては、たとえば、謙遜とかそういうような意味で、この「すみません」という言葉が悪いとは気づいていなかったのですが、先ほどの文章に、以下のふたつの意味が書かれています。
> 「すみません」という言葉には自己否定の意味合いがある
> また、自分が存在していること自体に謝罪している印象がある
実はこのことを薄々ながら感じることがあたっのです。
「すみません」というのは、謙遜というより、むしろ「自己否定に近い表現」ではないのかというような感じです。
漠然と感じていたことを、この本で突きつけられた感じで、その日から、私は「変えよう」と思ったわけです。
つまり、「日常生活の中で、すみません、を使わない生活にしていく」という方向に変えていくということです。
しかし、居酒屋やレストランなどで店員さんを呼ぶ時、そして、料理などを運んできてくれた時に「すいません」以外に何を使うのか、と最初は思いましたが、やってみると、あまりにも明白で、
・店員さんなど、人を呼ぶ時には「お願いします」
・料理や飲み物を持ってきてくれた時は「ありがとう」あるい相手によって「ありがとうございます」
これだけだったのですね。
「お願いします」と「ありがとう」で済むというか、それで良かったのです。
あと「すみません」は、謝ったりする際にも使いますが、それは「ごめんなさい」です。
それ以来、それを徹底すると、何かしてくれた人には「すみません」というより、「ありがとう」というほうがはるかにしっくりくることがわかりますし、変な話ですが、そう接した方が相手の対応が良いのです。
この「すみませんを言わない」は、そういうように意識的に始めまして、いまでも意識しないと、つい「すみません」と出そうになることはあります。たとえば、人にぶつかった時など、思わず、「あ、すいません」と言いそうになったりします。
それでも、以前と比べると、飛躍的この言葉が出ることは少なくなりました。
かつて一日に何度も口にしていたであろう「すみません」が、自己否定の意味合いを持っているとすると、
「すみません」と口にするだけで、「言葉で自分を否定している」
ということになり、そして、そういう「自己否定の暗示」を一日に何度もやっていたことになります。
これが良いことのわけはないです。
それに「すみません」を言わなくなると、「ありがとう」という回数が飛躍的に増えますので、それも悪いことではないのはないでしょうか。
この『腰痛は心の叫びである』に関しては、「腰痛は心の叫びである(山本浩一朗)」という本はとてもオススメ!というページで、かなり詳しく書かれてらっしゃる方がいらっしゃいました。
話は変わりますが、日本初のヨガ行者である中村天風さんは、「言葉が現実化する」ことを何度も言われていました。
だからこそ「口から出る言葉は肯定的でなければならない」と。
これに関しては、過去記事の、
・中村天風師の語る「極微粒子=気=創造主」の概念で 25年間持ち続けた「神様の正体のモヤモヤ」が少し晴れた日
2015/04/14
で書いたこともあります。
そこから一部抜粋いたしますと、以下のようなことを書いていました。
天風師が主張することは、言葉上は難しいものではなく、
・積極的な考えであること(否定的・消極的な考えを持たない)
・口から出る言葉を大事にすること(否定的・消極的な言葉は使わない)
・何にでも感謝すること
・信念を発布すること
・笑うことこのあたりです。
これは一見簡単そうですが、よく考えると、非常に難しい。
つまりは、商売で失敗しようが、病気になろうが、イヤなことがあっても、何でも「そのことに感謝して積極的に考える」ということですから。
しかも、偽りの心ではなく、「本心」で。
この「口から出る言葉」に関しては、言霊(コトダマ)という概念とも似ていますが、天風師のヨガの師匠カリアッパ師は、
「創造主によって便利な言葉を我々人間だけに与えられているが、言葉というものが、積極的に表現されたときと、消極的に表現されたときでは、直接的にその実在意識が受ける影響は非常に大きな相違がある」
と言っていたそうで、口に出した言葉は、健在意識から潜在意識へと影響を与えて、つまり、「発した言葉は、現実的に、その人に作用する」ということを何度も何度も言っていたそうです。
ちょっと長い抜粋になってしまいましたが、つまり、
> 「発した言葉は現実的にその人に作用する」
というのが、ヨガの教える本質であり、あるいは、名だたる宗教家たちを含む様々な賢者たちの述べていたことも同じようなことだと思います。
「言葉が実現化する」という意味は、心理的な意味においては事実です。それによって周辺世界まで変わっていくというのは、ややオカルトかもしれないですが、しかし、「すみません」を「ありがとう」に変えて以来の周囲の人たちの反応を見ていると、環境そのものが変化するというのも、それほどオカルトだとは言い切れない面もあるかもしれません。
そういうところから考えると、否定的な言葉が多くの病気などをもたらしても不思議ではないと思います。
すでに医学的研究において「肯定的な言葉によって、ストレスホルモンやハッピーホルモンの分泌に影響が出る」ことがわかっているわけで、そして、ガンや糖尿病を含めた多くの生活習慣病が、ストレスとの強い関係を持つことがわかっているのですし、「すみません」ばかり使うことの悪影響はありそうです。
そういうことを昨年から少しわかっていたのに、私は、毎日のように「すみません」と、自分を否定する言葉を口にし続けていたということになりますからね。
というわけで、まあ、この「すみませんを言わない」ということをオススメしたいということではないですが、「すみません」という言葉に自己否定的なニュアンスがあるのだとしたら、そういう言葉はあまり日常的に口から発しないほうがいいかなとは思います。
少しずつでも、日々の習慣を変えると、いつのまにか何かが大きく変わっている可能性だってあるかもしれません。
>> In Deep メルマガのご案内
In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。
▶ 登録へ進む