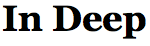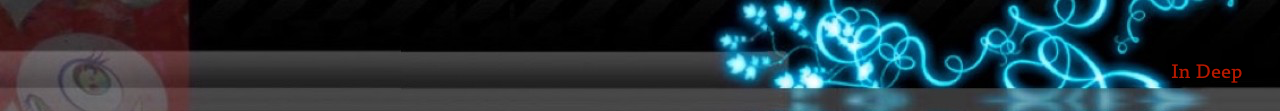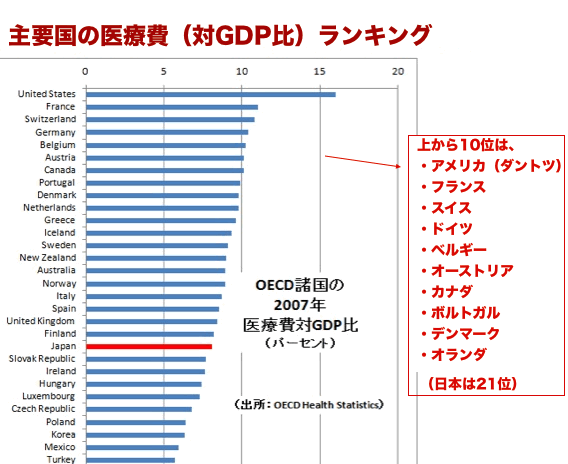チリで観測されたピンクの金環日食 2017年2月26日
2月26日は、南米からアフリカまでの北緯 33度線をまたいで金環食が観測されるという大変に不吉な一日となりました(そういう書き方はやめろよ)。
上の写真はチリで撮影されたもので、過去記事に出てきたこともありますが、チリの北緯 33度線の周囲というのは、何かというと「太陽がピンクになる」地域ではあります。
病気関係の記事が続いてしまいましたが、まだ一応養生中ということで、続きといいますか、前回の記事、
・「現代医学は悪しき宗教」と40年前に述べた異端医師の懺悔
2017/02/26
に関係したことを少しだけ書かせていただこうと思います。
寝たり起きたりしている合間に書いているので、前後の脈絡が破綻する可能性が高いことを最初にご了承下さい。
「医療異端者の告白」の補足
前回の記事は、かぜを引いた際、朝寝・朝酒・朝風呂(小原庄助さん)の中で読んだ『こうして医者は嘘をつく』(原題は「医療異端者の告白」)という本のことに少しふれました。
私自身は、医療と関わりを持たずに生きようとしてはいますけれど、「医療批判者」というわけではないですし、そもそも、こういうことは、基本的には個人個人の判断の問題だと思っていますが、現代医療をなるべく選ばないという選択自体を考えたことがないという方々が多いのが現実のような気もしますので、こういう本を読むのも悪いことではないと思います。
読んでバカバカしいと思えば、それでいいのですし。
私自身は、この「医療異端者の告白」の中で、メンデルソン医師が述べた「現代医学教」というように、今の医療を宗教にたとえる概念はとてもしっくりくるものではありました。
「ああ、何だか調子がおかしい。病院で見てもらおう」
(病院に行く。2時間待った後「何でもない」と言われ安心して帰宅する)
「ああ、良かった。病院に行って」
このように「意味のない時間を信仰心的な意義だけを感じて過ごす」ということにおいて、この流れは宗教以外では見られないような気がしますし、この形而上的な行為は日本中でものすごくたくさんおこなわれているような気がします。
「一日たりともそれを忘れてはいけない」という現代医療への忠誠と信仰心。
そういう信者の人々を何千万人と作り出すことが、国民皆保険制度の中で成し得られてきたことでもあるような気がします。
まあしかし、その国民皆保険制度自体が風前の灯火なのかもしれないですし、今は、その崩壊の日を粛々と待つしかないのかしれません。
メンデルソン医師は、「現代医学を構成する医者、病院、薬品、医療機器の9割がこの世から消えてなくなれば、人々の体調はたちどころによくなるはずだ」と、皮肉からでなく、本心で言っていましたけれど、多少そうは思います。少なくとも、いわゆる三大疾患は相当減ると思います。これは皮肉で書いているのではなく、検査されなければ見つからないという事実を書いているだけです。
しかし現状では、強制的にそういう時(健康保険制度の崩壊)が来るまで、そんなパラダイスが来るわけもないというのが現実です。
そういう意味では「国家システムの崩壊こそが健康を取り戻す最後のチャンス」というのは何とも皮肉な現代生活ではあります。
でも、最近は思うのですが、それでも、日本はまだマシというか、私はアメリカやヨーロッパの人たちがかわいそうで仕方なく思えることがあります。これらの医療先進国では、GDP と比較して膨大な金額が医療費につぎ込まれているのですが、「それと比例するかのように病気が多い」のです。
下は、医療費のランキングと、ガン発生率のランキングです。
あるいは、下は、アルツハイマー病の主要国の比較です。
主要11カ国でのアルツハイマー等の神経系疾患での死亡率の比較(男性 2009年)
1位 アメリカ
2位 フランス
3位 カナダ
4位 スイス
5位 スペイン
6位 オーストラリア
7位 イギリス
8位 イタリア
9位 スウェーデン
10位 ドイツ
11位 日本(アメリカの5分1ほど)
特に難しい解釈を加えたりせずとも、
「最新医療と最新予防医学を導入している国であればあるほど、何だかひどいことになっている」
ということがいえることは確かな気がします。
日本は、まだガンにしても、アルツハイマーにしても、他の疾患にしても、ヨーロッパなどから見れば低いですけれど、「先端医療の国のやり方に追従していけば」すぐフランスやオランダなどの「病気大国」に追いついていくと思います。
ガンの発生に関しては、過去記事、
・文明と医療と人々の健康知識が進んだ国であればあるほど…
2017/01/20
に記しました 2012年の WHO のデータでは、日本のガン発生率はさらに低く、全世界で 48位です(死亡率は 31位)。
人口10万人あたりのガン発症数の国際比較(青が濃いほど高い)
 ・WHO
・WHO
日本は、ヨーロッパ各国の医療先進国と比べると、あまりにもガンになる人が少ないですので、今は急ピッチでガン患者の急増の渦中にいるということなのかもしれません。いずれにしても、西欧の医療を崇拝している医療システムがある限り、日本のガン発生率はこれからもさらに増えそうです。
うつ病などを含めて、病気別にあげれば、もう本当にヨーロッパはボロボロで、ふと、
「誰かがヨーロッパを滅ぼそうとしているのではないか」
と思えるくらいです。
私は、ヨーロッパ各国の医療保健制度を知らないですが、恐らく日本の保健制度のようなものではないと思いますので、日本のように、「健康保険制度が崩壊すれば、幸せを取り戻せる」というほど単純ではないような気がします。
そういう意味では、ヨーロッパのいくつかの国は、長い年月の中で「病気で滅びていくのではないか」という気さえします。
ややかわいそうな気もしますが、放置していた受け手の本人たちの責任もあります。
ベンゾジアゼピンの問題は数十年前のアメリカで始まった
ところで、タイトルに「ベンゾジアゼピン」という文字がありますが、これについては、今まで何度か取りあげました。
私自身が 20年を越える服用者だった後に、脳の萎縮や、様々な後遺症だけを残して終わったということで、当事者的なことでもあります。まあ、若い時に大変にお世話になったものですので、恨みはないです。
これらについての個人的な体験については、最近の記事では、
・意図して書き始めたわけではないけれど、話はナルコレプシーと脳萎縮と「30年間におよぶベンゾジアゼピン系薬物依存」のことへと転がる石のように
2016/12/15
・子どもたちの未来。メンタル治療とリタリンやコンサータ。そして、私がかつて見たリタリン常用者たち
2015/12/17
などにあります。
しかし、このベンゾジアゼピンの問題が、40年前のアメリカにすでに同じように存在していたことを「異端医療者の告白」で知るのです。
その時でさえ、ベンゾジアゼピン系の精神薬は「歴史上、最も売れた薬」だったのですれど、その後、それらはさらに飛躍的に伸びています。
ベンゾジアゼピン系だけの売り上げの推移のグラフがどうしても見つからないのですが、「精神神経疾患治療薬」全般としては、下のようになっています。この中におけるベンゾジアゼピン系は相当なものとなるはずです。
ベンゾジアゼピン系での死者数も、この 10年くらいは特に増えていて、アメリカの場合は 2001年からのデータでは 5〜6倍以上になっています。
 ・US timeline Benzodiazepine deaths
・US timeline Benzodiazepine deaths
大事なことは、このグラフはオーバードーズ(過剰摂取)などが原因である場合が多く、つまり、「処方した医師が悪いのではなく、飲み過ぎた患者が悪い」ということを示しているということです。なので、処方が制限されることはありません。
そのようなベンゾジアゼピン系について、1970年代に書かれました「異端医療者の告白」では以下のように書かれています。ここにある「ジアゼパム系の精神安定剤」というのは、ベンゾジアゼピンの化合物のことです。
薬効などの詳細の各部については、40年の時間のタイムラグがあるので、今と違う部分もあるかと思いますが、大まかには当時の問題提起のままだと思います。
「史上もっとも売れる薬の秘密」より
適応症と副作用が同じという薬が存在する。つまり、その薬で効く症状とその薬で起こる副作用が同じなのだ。しかも、この種の薬は珍しくない。その一つが驚異的な売り上げを記録しているジアゼパム系の精神安定剤である。その添付文書を見ると、適応症と副作用がほとんど同じであることがわかる。
適応症: 疲労、抑うつ、激しい動揺、震え、幻覚、筋肉のけいれん
副作用: 疲労、抑うつ、激しい興奮状態、震え、幻覚、筋肉のけいれんこういう薬はいったいどんな基準で処方すればいいのか。この薬を処方して症状がつづく場合、どうすればいいのか。副作用を考慮して処方を中止すべきか、効能を期待して容量を倍にすべきか。こんな薬を処方する医者は、何を期待しているのか理解に苦しむところだが、一応、次の3つの推測が成り立つ。
1. 危険をおかしてもプラセボ効果を期待している。
2. 患者が苦しんでいる症状を増幅させる薬を投与することで、その症状を聖なるものとしてあがめようとしている。
3. 原始的な贖罪の儀式になぞらえ、投薬を中止したときに患者の症状が消えることを期待している。精神安定剤は年間6000万回も処方され、人類史上もっとも売れる薬となっている。たしかにこの薬にはそれだけの価値がある。適応症と副作用がほとんど同じこの薬は、科学・芸術・信仰が追求してきた「統一性」という理念を具現しているからだ。
最後の、
> 「統一性」という理念を具現しているからだ。
という文学的な表現の皮肉はさすがですが、当時でさえ「史上最高の売り上げ」を記録したこれらの系統の薬が、今はさらに記録更新となっています。
社会の状況を見ますと、これからも記録を更新していきそうです。
ここにある「適応症と副作用が同じ」というのは、大げさに感じる方がいらっしゃるかと思いますが、もし、ベンゾジアゼピン系の薬などを飲んだことがある方がいらっしゃるならば、そのどれでもいいですので、一般向けのインターネットのサイトで、薬効と副作用を調べてみるとおわかりになるかと思います。
たとえば、私が 25年くらい飲んでいたレキソタンという、ベンゾジアゼピン系の薬のページから抜き出しますと、こうなります。
[作用] 不安や緊張感をやわらげ、気持ちを落ち着かせます。
[副作用] いらいら、強い不安感、不眠、ふるえ、けいれん、混乱、幻覚、興奮、もうろう状態
日本で最も処方されているベンゾジアゼピン系の薬である「デパス」のページには下のようにあります。
[作用] 不安や緊張感をやわらげ、気持ちを落ち着かせます。
[副作用] いらいら、強い不安感、不眠、ふるえ、けいれん、混乱、幻覚、興奮、もうろう状態、息苦しい、起床時の頭痛・頭重感
私がベンゾジアゼピン系の薬を完全にやめることができたのは、故安保徹さんの本(どれか忘れましたが、安保さんはどの本も書いてあることは同じです)を読んだお陰で、その意味では安保さんは恩人でもあります。
30年近く飲んでいた私もやめられたのですから、時間はかかると思いますが、誰でも、ベンゾジアゼピン系の薬をやめることはできると思います。
というようなことで、前後内容がバラバラでしたが、久しぶりに引いたかぜの中で、書かせていただきました健康関係の連投でありました。
>> In Deep メルマガのご案内
In Deepではメルマガも発行しています。ブログではあまりふれにくいことなどを含めて、毎週金曜日に配信させていたただいています。お試し月は無料で、その期間中におやめになることもできますので、お試し下されば幸いです。こちらをクリックされるか以下からご登録できます。
▶ 登録へ進む
昨年度は読者様たちのお陰で「まぐまぐ大賞2019 コラム賞1位」を頂きました。受賞ページはこちらです。