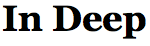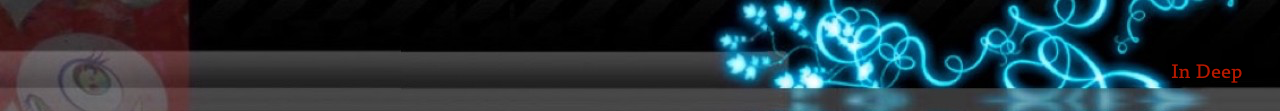432Hzと440Hzの人体への影響に「差異がない」ことも判明
2019年6月4日の米メディアの記事より
今回ご紹介させていただきます内容は、私個人にとっても、非常に勉強になるものでもありました。
これは「音楽は人間の治療に作用するかどうか」ということについて、おそらく初めて具体的な音楽の効果を導き出した科学的実験だと思われます。
以前、以下の過去記事を書かせていただいたことがありますが、今回の記事はそれと関係しているかもしれません。
【重要】 ピタゴラスが2500年前に述べた「病気は音で治療できる」という主張に対しての本格的な試験が始まる。現段階でわかっていることは、細胞内のひとつの繊毛が周波数に対して反応するということ
今回ご紹介させていただく記事は非常に長いものですので、まずは、その記事をご紹介させていただきたいと思います。
なお、この実験では、おそらく科学的な実験として初めて「 432Hz と 440Hz 」の差異の試験もしています。
結論を先に書いておきますと、この試験においては、「そのふたつに差はなかった」というような、これはこれで意外な結果となっています。
しかし、それよりも「音楽の身体への影響」はこのようなものだということを、初めて知ったことが大きいです。
ここからです。
Testing a 2,500 Year-Old Hypothesis
greenmedinfo.com 2019/06/04
2500年前のピタゴラスの仮説の検証が始まった
音楽は、古い血球に新しい生命を吹き込む可能性がある
序論
古代ギリシアの数学者であり哲学者であったピタゴラスは、音楽は、医療の代替として使用できると確信していた。彼は、音楽は健康回復に大いに関与していると主張した。
それから 2500年が過ぎた今、音楽療法は、例えば、うつ病患者などの精神的支援や不安感の軽減等に重点を置くような臨床分野とはなっている。音楽療法は、メンタルに問題のある患者たちに対してセラピストによる回復の促進を助けるという点では認められている。
しかし、それ以外では、現代の医療の現場で音楽療法が有効に使用されている例はほぼない。
音楽療法の有効性を実証するための研究は、これまで多く行われてきたが、現在、特定の疾患の治療としての音楽の実証可能な利点に焦点を当てている「音楽医学」の分野への関心が高まっている。
音楽が医療として成立するとされる定義のひとつは、「セラピストがいなくても、音楽を聴くことに医学的な意味がある」ことだ。
たとえば、疾患の治療と予防の医療テクノロジーに関するプロジェクトであるコクラン共同計画のライブラリーには、2013年の「冠状動脈性心臓病患者のストレスと不安の軽減のための音楽使用」というタイトルの分析書類がある。
これは、計 1369人の参加者による 26の音楽医療に対してのコクランによる分析で、その結論は、「音楽を聴くことは、収縮期の血圧と心拍数に有益な効果がある冠状動脈性心臓病を患っている人の場合、心筋梗塞の不安を軽減するのに効果的であると思われる」とある。
また、「音楽を聴くことで、痛みや呼吸数を減らすことができ、心臓手術や手術後の患者たちの睡眠の質を改善する」と記されている。
アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の医学部は、病気への対処における音楽の役割を認識しており、そのプログラムの中で、音楽で治療を試みている様々な疾患を提示している。そこには、パーキンソン病や認知症などがある。
しかし、以下に記載する本研究は、「音楽医学の定義の拡張の必要性」を示している可能性がある。すなわち、患者の全身あるいは体の特定の部分が、特定の音楽や音圧レベルに浸されることによる体内の変化が示されているのだ。
これは、ヘッドフォンまたはスピーカーを介して音楽を聴くことに関連する利点とは異なり、そのような音楽分野または特定の音の周波数への没入は、測定可能で有益な生理学的効果を提供し得る。
赤血球の寿命に及ぼす音楽の影響を試験するための実験
音楽と健康に関するピタゴラスの信念に触発され、2015年の初めにジョン・スチュアート・リード (John Stuart Reid)博士は、その 2500年前の仮説を検証する実験を考案し、ヒトの細胞寿命に対する音楽の影響を検証するための試験管内実験(In vitro)を計画した。
2017年初頭、検査対象のヒト細胞の供給源として、ヒトの血液を使用することが提案された。
その後、2017年末に、資金援助の入札が開始され、2018年初めまでに、いくつかの音楽関係企業や医療関係者などからの大きな支援があり、実験の資金は確保され、研究の基礎となった。米ラトガース大学の 3人の研究者が、2018年初頭に最初の実験を行った。実験の結果は非常に有望であり、その後、2019年5月に、次の段階の実験に入った。
実験の方法
血液型 O型の女性ドナーから採取した血液を実験用の小瓶に入れ、実験室用の冷蔵庫内で 4℃の温度で保存した。
実験の際に、実験用小瓶を冷蔵庫から取り出し、ゆっくりと周囲の温度を上げた。実験室での平均気温は 23℃だった。そして、血液の入った実験用小瓶を振動機で 30秒間振動させ、次いで、ピペット(測定用の小さなガラス管)を用いて、2つの小瓶にわけた。
1つの小瓶を、音響メーカー SMSL 社のデジタルアンプ SA-36A とソニーのスピーカー SS-TS3 が配置されている実験音楽室にある 37℃に保たれている培養器(インキュベーター)に入れた。
音楽の信号は、アップル社の iMac を用いて、さまざまなフォーマットの音楽にアクセスした。
それから、音楽培養器に入れた小瓶を、平均 85dBA (単位はデシベル。音の大きさをあらわす)の音楽がある音場に 20分間浸した。音圧レベルは、キャッスル社の騒音レベル測定器 GA214 で測定された。
血液の入った小瓶のうちのひとつは、選ばれた音楽のうちの、ひとつにだけ浸された。なお、実験には、ホワイトノイズ(テレビの放送がない時に流れるような単にザーッという音の連続のこと)が含まれるが、これは、クラークテクニック社のオーディオアナライザ DN6000 により作られた。
もうひとつの小瓶の対照血液は、音楽に浸された小瓶と同じ 20分の間、ファラデーケージ(金属の箱)の中の非常に静かな環境(音楽のない環境)にある培養器(温度は 37℃)に入れた。
20分の試験期間の直後に、各小瓶の血液を pH 7.41の緩衝液で 200:1 の比率で希釈し、続いて染色剤と混合し、ナノエンテック社の自動細胞計数器により細胞の数を計測した。
実験の結果
2018年初頭におこなわれたクラシック音楽で行われた 2つの試験では、音楽がある環境と、音楽のない静かな環境では、それぞれ生きた赤血球の数の比率に優位な差があることを示していた。
今回の試験では、クラシックだけではなく、さらに、ピアノ、ギター、女性ヴォーカル、男性ヴォーカル、聖歌隊、ラップ、ダンス/テクノ/ハウス、ハープ、ゴング、スピリチュアル志向の音楽、そしてアコースティックギターのサウンドを含む、いくつかの他の音楽ジャンルにより、生きた赤血球の細胞数の変化がテストされた。
その結果を以下の表1および表2にまとめた。
音楽の著作権保持と、機密保持のために、具体的な曲名や 1mL 当たりの赤血球の実際の数値は示さない。その代わりに、音楽に浸された環境における生存可能な赤血球の数と、音楽のない静かな環境における生存可能な赤血球の数との比率を示した
表1は、音楽ジャンルの3つのセクションからの結果を示している。そして、それぞれ 432Hz、440Hz、444Hzの 3つの異なるのピッチ(基準音)での結果も含まれている。
(※ 訳者注 / この下の表の数値はちょっとわかりにくいかもしれないですので、先に書いておきますが、たとえば、「 7.93 対 1 」)というのは、「静かな環境に置かれた血液の生きた赤血球細胞が 1 」なのに対して、「音楽に浸された血液のほうは生きた赤血球数が 7.93」だったということで、音楽に浸されたほうは 8倍近く生きた赤血球が多かったということだと思います)
《表1》「音楽に浸された20分後の生存している赤血球数」と「静かな環境にいた20分後の生存している赤血球数」の比較
・クラシックのオーケストラ、ハープ、ピアノ → 2.22 対 1 から7.93 対 1 の間
・ラップ、ポップ、ロック → 7.33 対 1 から、23.4 対 1 の間
・男性ボーカル → 2.1 対 1 から 10.7 対 1 の間
様々なピッチ(基準音)で様々なアーティストによってテストされた多くの楽曲は、血液中の生存可能な赤血球の数の大幅な増加を示した。
また、3つのピッチ(432Hz、440Hz、444Hz)すべてにおいて、生存可能な赤血球の数の範囲に関して同様の結果を示した。つまりも、このうちの、「どのピッチが最も生存した赤血球が増加したか」ということについての顕著な差はなかった。
表2は、432 Hzと440 Hzの2つのピッチでの、それぞれのジャンルの音楽選択の結果を示している。繰り返しになるが、432Hzも 440Hzのどちらのピッチも、どちらかが試験において優位が示されることはなかった。
《表2》「音楽に浸された20分後の生存している赤血球数」と「静かな環境にいた20分後の生存している赤血球数」の比較
・女性ボーカル → 5.26 対 1
・女性ボーカルと演奏 → 18.1 対 1
・音程を声で発声 → 4.13 対 1
・ダンスミュージック(テクノ-ハウス) → 14.42 対 1
・音楽療法の装置が出す音 → 11.72 対 1
・ゴング → 5.5 対 1
・東洋の精神的な聖歌 → 17.69 対 1
・ホワイトノイズ(85デシベル) → 4.61 対 1
・ホワイトノイズ(105デシベル) → -0.21 対 1
結果からの議論
音楽に浸された全ての血液試料が、静かな環境に浸された試料よりも多くの生存可能な赤血球を産生したというデータが全体的なパターンとして見られたが、音楽のジャンルなどによって、著しい差があることを示している。
そして、この結果からの問題は以下のとおりだ。
「音楽が、赤血球の数を増やすメカニズムは何なのか」
この効果のメカニズムは不明としか言いようがないが、ただ、実験室での赤血球の寿命は、生と死の間の移行状態を経ていると仮定することができる。
細胞の若返りのこの仮説的な過程を助けることができる頻度への指標は、音楽ジャンルとの関係を示した結果表から集めることができる。
例えば、女性ボーカルだけの場合(5.26 対 1)と、バック演奏を有する女性ボーカルの音楽(18.1 対 1)との間の赤血球生存率には有意な差がある。
バック演奏には、低域が含まれる(※ 訳者注 ベースのことだと思います)。また、テクノ-ハウスのダンスミュージックやもポップスなどにも、低音が含まれる。
クラシック音楽の 2つの選択されたジャンル(ハーブやピアノ)には、特別な低周波が含まれていない。
仮説として、ポピュラー音楽の低周波は、鼓動する心臓音と似た音を生み出すだけでなく、ある意味では赤血球への影響の観点からは同じもののように振舞うのかもしれない。低周波音は、各心拍によって提供される低周波圧力がヘモグロビン分子が酸素を取り込むのを助けるメカニズムに寄与し得る可能性もある。
これが事実であることが証明されれば、実験での全血中の溶存酸素から獲得された赤血球の酸素化の増加により、(音楽が)細胞を活性化させることを説明することができる。
試験では、選択したほぼすべての音と音楽で生きた赤血球が増加したが、ただ「 105デシベルのホワイトノイズ」だけは、20分以内にほとんどすべての赤血球が破壊され、赤血球膜が破裂する溶血が起きたと考えられる。
また、今回の試験では、「 A4 (いわゆる「ラ」の音) = 432Hz」のピッチでチューニングされた音楽と、「 A4 = 444Hz 」のピッチでチューニングされた音楽に対しての試験も提案されて、それを行った。
432Hzのピッチに肯定的な人々は、432Hz の音楽は(現在の基準音である 440Hz より)滑らかで自然に感じられると報告することが多いが、一方で、444Hzのピッチを支持する人々は、他の音のピッチにも DNA を修復する能力があると考える。
これらの主張を試験することは、現在の私たちの研究の範囲を超えているが、しかし、今回の試験の結果は、3つの異なるピッチ( 432Hz、 440Hz、 444Hz )で作成された音楽選択の間に大きな違いは示されなかった。どのピッチでも、同じように、赤血球の生存率の増加を示した。
今回は、試験管内での実験 (in vitro)であり、今後、生体を使った実験 (in vivo)で、同様の結果が見出されるかどうかを試験する必要がある。
ここまでです。
この実験が示したことの中で最も意外だったのは、つまりは、
「何となく漠然と考えられていることと逆」
になっていることでした。
たとえば、まあ、「何となく」ですけれど、「激しい音楽より、穏やかで心安まる静かな音楽のほうが体にも心にも良さそう」というように漠然と思ったりしますが、この結果は、たとえば、
「クラシック音楽のハープやピアノ」は、優しそうな音色ですけれども、それと、ラップやロックと比べると、
「ラップやロックのほうがはるかに生きた赤血球が多く作られている」
ことが明白となっています。
つまり、血液に関して言えば、激しい音楽のほうが、「細胞がどんどん健康になる」ようなのです。
上の表では、
・クラシックの場合、最も低い数値だと、静かな場合と比べて「 2倍」ほど
なのが、
・ラップやロックでは、最大で、静かな場合と比べて「 23倍」ほど
というように、後者のほうが大幅に「細胞が活性化している」ことがわかるのです。
テクノなどのダンスミュージックも、赤血球が大幅に上昇しています。
これらの結果を見ていますと、
「うるさい音楽のほうが、体にいいってことなの?」
と私は悩んでしまいましたよ。
しかも、432Hz と 440Hz の差異も、「生きた血液の増加」という面だけに関しては、「差がない」というのです。
とはいっても、432Hz と 440Hz の差異は、「実感」として感じるものですので、血液への作用という部分の他として、必ず、特にメンタルへの作用が強くあると私は思っていますけれど、少なくとも、血液細胞に対しては、どちらも同じだったようです。
まあ、私自身、日々、非常にうるさい音楽と、とても静かな音楽のどちらも交互に聞き続けているヒトですけれど、結局は、
「音楽はどんなものであっても、あからさまに健康に影響を与えている」
というひとつの事実が,この実験にあらわれているように思います。
何でもいいようなのです。
ただ、実験の中で「唯一」赤血球が破壊されたのが、
「 105デシベルの音量のホワイトノイズ」
だったことは、また示唆的です。
ホワイトノイズというのは、いわゆる「ノイズ」ということでよろしいかと思いますが、105デシベルというのは、比較的壊滅的な音量で、たとえば、騒音の目安から見ますと、
「電車が通る時の地下鉄内の音 100デシベル」
「直近での車のクラクション 110デシベル」
ということですから、人間がそういう騒音に曝されている時、「その血液は死に続けている」と考えても良さそうです。
人間は騒音環境の中では長く生きられないものなのかもしれません。
いずれにしても、「人間の身体は、自らの健康回復のために常に音楽を欲している」ということは、ある程度事実のようですので、デスメタルでもモーツァルトでもチャンチキおけさでも何でもいいですので、私たちは音楽を聞きながら生きていくのがいいようです。